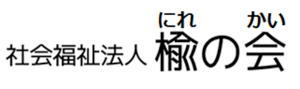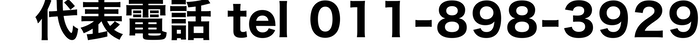印刷用PDFはこちら ★★★ 今月のエピソード ★★★ 11月16日(木)すいかクラスの『きらめきママの子育てサポート講座』の4回目を行いました。 6名のお母さんに参加頂き、1~3回目の復習と“図星を言うが大切な理由… もっと読む »
楡の会発達研究センター
こどもクリニック院長 石川 丹
(現・名誉院長)
楡の会は障がい児者の方々の発達援助をしていますが、発達援助方法は心理学、教育学、医学などの科学の進歩に伴って変わり、新しい援助方法が日々研究開発されています。
発達研究センターはそうした発達研究をするとともに、世界中で研究されたり実践されたりしている発達援助方法に関する情報を収集研究する場であります。
私たち自身の研究成果も札幌のみならず北海道の内外に発信したいと思っています。その上で、多くの方々と御一緒に障がい児者支援を推進したいと望んでいます。
楡の会に通う方々の発達をうまく援助できた場合、つまり発達の心配が少なくなった方がいたら、どうしてうまく行ったのかを分析考察し、その発達メカニズムを明らかにして、他の利用者さん、その次に見える方々にも生かせるように工夫して行きたいと思っています。
以下に随時論文を掲載します。
(51)楡の会発達研究センター報告、その51(2021年4月)
“好い事作り療法”ケースカンファレンス:保育園看護師研修会 印刷用PDFはこちら “好い事作り療法”ケースカンファレンス:保育園看護師研修会 こどもクリニック 児童発達支援センター 名誉院長 石川 丹あかし … もっと読む »
(50)楡の会発達研究センター報告、その50(2021年3月)
子育て親育ち読本 I・II・IIIの読後感想意見質疑応答 印刷用PDFはこちら 子育て親育ち読本 I・II・IIIの読後感想意見質疑応答 こどもクリニック名誉院長 石川 丹あかし 初めに 以下は「子育て親育ち読本」を読… もっと読む »
(49)楡の会発達研究センター報告、その49 (2021年2月)
苦しい時期もあったけど、代弁して、安心を伝えてきたからGがぐっと成長した! 田野 準子 古谷 ゆき江
(48)楡の会発達研究センター報告、その48(2020年12月)
言葉の遅れのため3歳4歳で来院し挽回した20人 石川 丹
(47)楡の会発達研究センター報告、その47(2020年11月)
「僕の気持ち伝えている!分かってほしい!」のAくんの発達
(46)楡の会発達研究センター報告、その46(2020年10月)
たくさんうけとめてほしい!H君の“わかってもらえてる感”作り
(45)楡の会発達研究センター報告、その45(2020年5月)
気性の激しい子への精神療法:自己対象化を育てられた1例 武部裕子・石川 丹
(44)楡の会発達研究センター報告、その44(2020年3月)
攻撃から指導への発達 石川 丹
(43)楡の会発達研究センター報告、その43(2019年11月)
続・音韻の発達~音声学・音韻プロセス・音韻練習・その子語の研究 石川丹